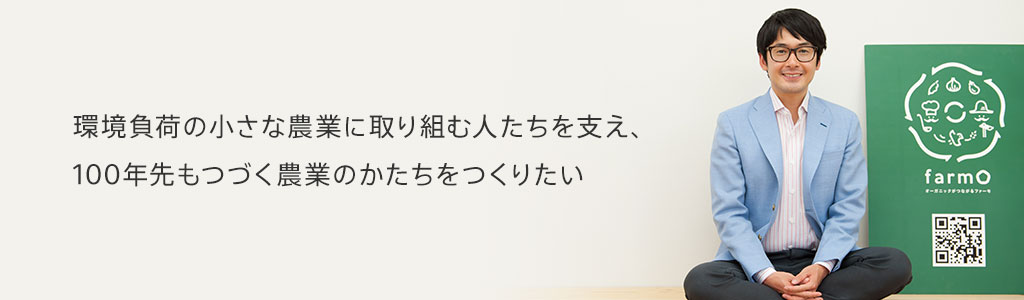Sony Bank GATE
ストーリー
世界的によく知られる観光地の京都だが、聖護院大根や賀茂なすなどの京野菜で知られる農産地としての一面も併せ持っている。その京都の地で、「環境負荷の小さな農業に取り組む人たちを増やし、100年先もつづく農業のかたちをつくること」を目標に2009年に設立された株式会社坂ノ途中。野菜提案企業を称する同社の多彩な取り組み、その事業に込められた想いを代表取締役の小野邦彦氏にうかがった。
新規就農者を支えることが環境への負荷が小さい農業の拡大につながる
大学生の頃、バックパッカーとしてアジア圏を旅して回っていた小野氏。そのとき、目にしたものが、現在の事業を立ち上げるきっかけになったという。
「いろいろな場所の遺跡巡りをしていて、はたと気付いたんです。遺跡とは社会が終焉を迎えた、その残骸なんだと。遺跡は世界中にありますよね。そのぐらい社会は脆い。何も努力せずに放っておくと終わってしまうのだと感じたんです。同じ目線で現代の農業を見たときに、これはかなり危ういなと思いました。低コストや安定的な大量生産を実現するために、農薬や化学肥料、化石燃料などが大量に用いられ、その結果、農業は水質汚染や環境破壊の要因となり生物多様性も損なわれています。この状態が続いたなら100年先まで続けられないのではないかと思ったんです。そこで、100年先も続けられる、環境への負担が小さい農業を広めていくことが大切だと感じ、現在の事業を始めました。」

小野氏が着目したのは新規就農者だった。後継者がいないため廃業する農家が増えていく一方で、社会との関わり方を模索し使命感を持って農業の世界に飛び込む若者たちが少なからずいる。そんな新規就農者を支えることが、環境への負担が小さい農業の広がりを生むのではないかと考えたのだ。
「新規就農者は、それぞれ志を持って始められるかたが多く、土作りを重視した有機栽培、季節にあわせた農産物を育てるような環境負荷の小さい農業に取り組みたいというかたが多いんです。また、自らの意志で農業に挑戦するかたたちなので、栽培方法などの勉強もしっかりされています。ただ、なかなか農産物の売り先、販路をつくることができません。安定供給できる生産者が優先されるのが農産物流通の常識です。新規就農者は空き農地を借りて始めるため、いくら熱意があってもスモールスタートになってしまいます。新規就農者の少量不安定な農産物を流通させるしくみがなければ、経営は成り立たないのが実情です。思いを持って就農したけれど、貯金が底をついて離農してしまうケースも多い。その問題の解決を目的に事業をスタートさせました。」
社名である『坂ノ途中』とは、成長途上にある新規就農者を支えるパートナーでありたい、という思いを込めて命名されたという。
宅配事業をベースに、飲食店や小売店への提供も実施
現在、『坂ノ途中』の事業の柱となっているのは、個人客を対象とした野菜セットの定期宅配。仕入先となる提携農家は関西を中心に四国・九州の約200軒。そのうちの8~9割が新規就農者だという。
「こんなに新規就農者の人たちと仕事をしているのは、日本でも僕らぐらいでしょうね(笑)。効率至上主義の農業ではありませんから、栽培の方法や、野菜の品種もさまざまです。一般的には、トマトならこれ、ピーマンならこれ、というように栽培しやすい品種がある程度決まっているのですが、彼らは挑戦意欲が旺盛なので、あえて違う品種を選ぶケースが多い。それによってニンジンは4色ぐらいあったり、ナスだけでも6~7種類ある。だから年間400種類ぐらいの野菜を扱っています。定期宅配する野菜は季節によって表情も変わっていきますし、見たことのない野菜に出合うこともあるはずです。野菜の味とともに、そういったことも楽しんでいただければと思っています。」

同社では宅配事業の他に、飲食店や小売店への卸販売も行っている。また、京都と東京(現在閉鎖中)には、小規模ながら直営店舗『坂ノ途中soil』を構え、個性豊かな野菜をお客さんが手に取り、購入できる場をつくっている。
加えて、同社が展開する事業に『就農準備トライアスロン』というユニークなプロジェクトがある。これは、自社農場『やまのあいだファーム』にて6泊7日の「リアルな」農業体験を行うというもの。
「農家になると意思を固めて会社を辞めたものの、実は虫が苦手だったなんてことがそこで分かったんじゃ目も当てられないじゃないですか。実際、そういう人っているんですよ。とはいえ、会社勤めをしながらでは、農業という仕事が見えないから、意思決定が難しい。それならば一週間の有給休暇を取って京都へ来て、リアルな農業の現場を体験してみませんか、というプログラムです。これまでに受講者の3分の1が、意思を固めて就農されています。」
『坂ノ途中』は新規就農者をサポートするだけではなく、就農を考えている人へのサポートにも取り組み、多方面から環境負荷の小さな農業の拡大に向けて尽力している。
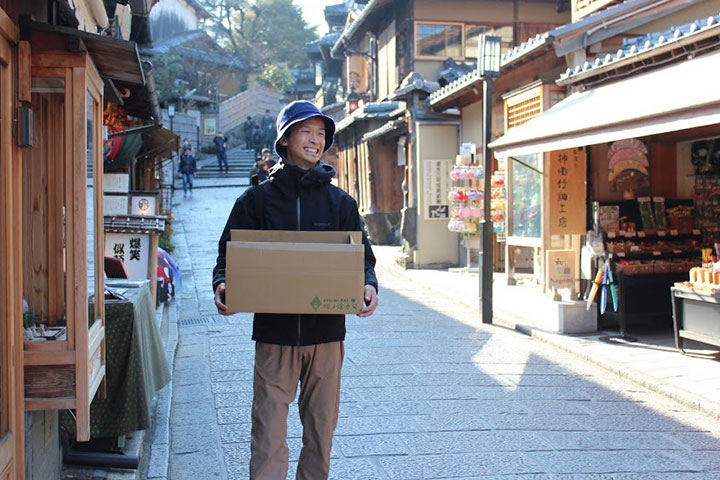

ブレることのないビジョンをベースに東南アジアでもプロジェクトを展開中

2017年から『坂ノ途中』が事業として取り組んでいるのが、生産者とバイヤーのWebマッチングサービス『farmO(ファーモ)』。京都に拠点を置く同社は、地理的に提携が難しい生産者や取り扱いが困難な野菜がある。一方で、オーガニックの野菜を仕入れたいが生産者が見つけられないバイヤーや飲食店が存在する。おたがいが抱える問題を解決するためのコミュニケーションの場が『farmO』である。
「会社をスタートさせて分かったことは、オーガニックな野菜を扱いたいとか、その生産者を支えたいと考えているレストランのオーナーや小売店主が全国にいるということです。産地へ足を運び、生産者と話をして信頼関係をつくっていくのは理想ですが、小規模な店舗では、営業を止めて生産者訪問するということが難しい。情報交換や直接取り引きをサポートすることで、未来につながる農業の普及を加速させたい、そんな思いから始めたマッチングサービスです。」
現在、400軒を超える生産者と200軒を超えるバイヤーが登録し、情報交換や取り引きを行っているが、システムの修正や機能の追加など、さらなるバージョンアップが図られている。
また、環境負荷の小さな農業を広める『坂ノ途中』のプロジェクトは国内にとどまらず、海外でも着々と進められている。それが、豊かな森を未来に残すことを目的とした『海ノ向こうコーヒー』プロジェクトである。“森をつくる農業”と呼ばれる『アグロフォレストリー』農法を参考に、森の樹木がつくる日陰でコーヒーの木を栽培し、良質なコーヒー豆の収穫と森の保護を両立させたもので、すでに、ラオス・ミャンマー・フィリピン・タイ・イエメン・バリ・ネパール・中国でプロジェクトが進行しているという。
「海外事業としては、2012年から5年間、JICA(国際協力機構)などとともにアフリカのウガンダで有機農業の普及活動を行ったことにはじまります。その後、事前調査でコーヒー栽培の可能性に着目し、『メコン オーガニックプロジェクト』をスタートさせ、活動エリアが他国にも広がったため名称を『海ノ向こうコーヒー』に変更しました。」
地域の人々が良質なコーヒー豆の栽培によって生活が安定すれば、森を切り開く必要がなくなる。収穫されたコーヒー豆は日本に輸入され、コーヒーが育まれたその土地ごとの豊かな味わいを我々は楽しむことができるというもの。『坂ノ途中』は、環境負荷の小さな農業を広めるというミッションをベースに、民間レベルの国際協力を行っている。それも、両者にとって無理のないかたちで、win-winの関係を築けている点に、同社の特徴や良心を強く感じる。
このように『坂ノ途中』では、複数のプロジェクトが同時進行している中、国内の物流機能の拡大が当面の課題だという。現在、京都と東京(港区、目黒区、渋谷区、世田谷区など)にて自社便での配達を行っているが、温度管理を徹底し、より新鮮な野菜を届けるため自社便エリアの拡大を図っていくという。
安全でおいしい野菜作りという食の観点から環境保護を行う同社の取り組みは、今後大きな意味を持つだろう。だが、生産者も同社も、まだまだ坂の途中。多くの人たちの後押しが必要なのである。