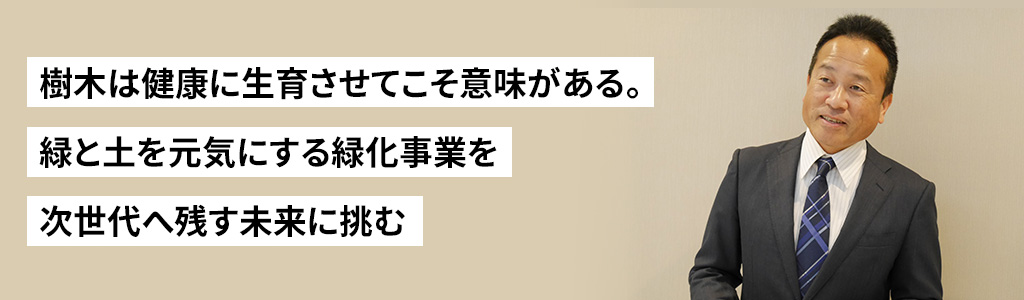Sony Bank GATE
ストーリー
関西圏と関東圏を中心に造園と施工・管理を手がける株式会社Kei'sは、緑化事業と樹勢回復という樹木を健やかに生かす技術を持って、1999年の創業以来、順調に事業を拡大。目標として掲げる「世界の緑を元気いっぱいにする」という信念はぶれることなく、日本の街、住宅のみならず東南アジア各国・地域にも広がりを見せている。ただ植樹するだけではなく、その成長まで見通す緑化の鍵は、そこに集まってくる昆虫や鳥といった生物、果ては人間に与える影響まで視野に入れた環境づくり、さらに土壌のメンテナンスにあるという。そうしたビジョンと方法論をいかに獲得してきたのか。代表取締役の河内 進氏に話をうかがった。
その地域のリアルと向き合うことによって、海外の緑化事業は初めて可能性が広がる
20代前半、自分の歩むべき道を探す河内氏の指針となったのは、「幼い頃から感じていた、元気のいい緑の中にいるときの心地よさ」だったという。当時の報道で知った、世界中で進む森林の劣化・減少という現実も背中を押した。そこで、緑化のエキスパートとなるべく造園会社に就職した河内氏だったが、働くうちに手がけたい方向性との大きな距離を感じていた。
1999年に河内氏は造園業者として独立。サラリーマン時代の取引先からのサポートもあり、2003年には法人化するに至った。事業目的はもちろん「世界の緑を元気いっぱいにすること。」社員にも恵まれ、2005年に念願だった海外での緑化活動の一歩を踏み出した。中国の内モンゴル自治区クブチ砂漠にて、ボランティアとして初の植樹に挑んだのだ。

「振り返ってみれば、知識と経験がまったく不足していました。生育に必要な雨が不足していることに加えて、砂漠が風で移動してしまうため根を張ることが難しく、樹木自体が倒れてしまうのです。」そこで、今度は樹木が育ちやすい気候の東南アジアに着目。タイにおいて、政府や自治体の協力を得て苗木3,000本を植樹した。「植える木の種類に規制があったので7割は地元の在来種。そして、現地の人の将来の利益になればと果樹を3割。」緑化活動は、そこに住む人の生活を潤すためのものでありたいという、河内氏の判断だった。
その後、植樹活動は4、5年をかけてベトナム、カンボジアへと継続された。
「5年目になって、ふと、タイに植えた樹木はどんなふうに育っているのだろう、行ってみるかと思い立ちました。」と、河内氏が現地を訪れ、目にしたのは思いがけない光景だった。辺り一面雑草に覆われ、木をどこに植えたのか、その痕跡もない。原因を調べたところ、手入れされることなく放って置かれたために枯れ果て、伐採され燃やされたという。果樹も成長までに年月を必要とするため、それまで待てない現地の人たちには、まったく興味を持ってもらえなかったのだ。

緑化の前に、地元の人に樹木を生かすメリットを知ってもらわなくてはいけないと思い知った河内氏が考えついたのは、果樹の花の蜜を収穫する養蜂だった。早速、知識と技術を学び、1年後にはベトナムの山岳地方バグジャンのライチ畑に蜜蜂の巣箱を置いた。しかし、そこでも厳しい現実に直面した。年7回の農薬散布期間中は巣箱を移動しなくてはならなかったが、住民とのコミュニケーション不足から、知らない間に撒かれた農薬により蜜蜂は全滅してしまった。そこで河内氏は、さらに根本的な問題に思い至る。
「蜜蜂がそのまま生き残ったとしても、その蜂蜜は販売に適さなかっただろう。また、農薬は地面から用水路へ、その先は川へ海へと流れていく。環境のためにも住む人のためにも、その土地の農業にも意識を向けなくてはならない。」

人間と多種多様な生物の共生共存を叶えるために、力強い樹木を育てたい
現在、河内氏はベトナムで法人を立ち上げ、無農薬の野菜を育てて販売している。野菜の生産は緑化活動とは言いにくい面があるが、そこから次のステップである果樹へ、さらにそこから樹木へと緑化に結び付けていきたいという。
「緑や果樹の恵みに恩恵を感じてもらうには、将来の利益よりも、そこに住む人々の経済的なゆとりを進行形で担保することを考えよう。」河内氏は、それまでの試行錯誤から、土地の実情を知り文化を理解して初めて現実的な緑化が可能になるというセオリーを獲得したのだった。今、ベトナムではもう一度、蜜蜂の手配を進めている。新型コロナウイルスの影響で休止しているが、地元の信頼と協力を得て再挑戦が始まりつつあるのだ。

もちろん、こうした海外での時間をかけた緑化事業を推進できる背景には、株式会社Kei'sの基幹事業である、関西圏と東京を中心とした造園業とその施工・管理の業績があり、そのバックアップがあるのはいうまでもない。売り上げの6〜7割は公共事業からの受注で、堅実な成長を遂げている。
だが、その一方で、「だからこそ今、社員には緑化事業の意義と重要性を知り、仕事としての意識にシフトしていって欲しい。」と河内氏。そのアプローチのひとつが、大阪の堺営業所で行っている「人と多種多様な生き物が共存できる事務所」のモデルづくり。5年前から、約1,500坪の土地に小川と滝・池を造成し、在来種の樹木を植え続けている。
「久しぶりに訪れる人は樹木の成長ぶりに驚きます。虫が苦手だった社員も、樹木と共存する毛虫や蝶などを間近に見るうちに興味を持ち始めました。」

虫をエサにする鳥も飛来するようになったという敷地には、さらに植樹を進めていくという。河内氏が目指しているのは、人間がただ癒されるだけではなく、さまざまな動植物と触れ合うことができる、ひとつの生態系を持つ空間なのだ。
「完成までにはまだまだ時間がかかりますが、ゆくゆくは中に保育園を開園するなど、子どもに解放できるような空間にしていきたいと考えています。」
そこで効いてくるのが、株式会社Kei'sの自然環境を生かす造園技術である。ただ木を植えるだけでは健やかに育つことは難しく、雑草だらけで人にとって心地よい空間とはならない。植栽のプロが手を入れることによって、樹木を健康に保ち、生き物との共生を可能にする。この緑化事業を、カフェの設計や都市計画にも提案していきたいという河内氏。「アジアでは日本の庭園が高く評価され、ステイタスがある。」と海外での展開も視野に入れている。

造園業の将来のために、アカデミアの協力を得て樹木の成長に適した土壌を開発
そして今、株式会社Kei'sは事業をさらに発展させるため、大学との連携も深めている。立命館大学の協力を得た、樹木の生育に適した土壌の開発である。同大学生命科学部では野菜を育てるためのバクテリアや微生物が豊富に含む土を研究しているが、それを樹木にも生かしたいと河内氏は期待する。
「立命館大学びわこキャンパスのグラウンドの周りに植えられた桜の木は、土壌が良くなくて、半分近くが元気のない状態です。そこで土の有機質を増やして、土中環境の改良にチャレンジしています。」
考えてみれば、山の樹木はなぜ活き活きと生い茂り樹勢がいいのか。その理由は河内氏曰く、「恵まれた土壌に育まれた樹木は、人間でいえば強い免疫力を持っているようなもの。」だからこそ悪い虫を寄せ付けることもないのだという。

「マンションやオフィスビルなどのエントランスの植栽も、植えっぱなしにしておいて土に気を配らなければ、樹木が元気な状態を保つことはできません。そういうことを一般的な知識としてぜひ広めていきたいという思いもあります。」
住宅地やオフィス街に元気のいい緑を育んでいけば、それが点となり、その点が増えていくことで、やがては豊かな緑化へつながるだろう。
河内氏にとって、「世界の緑を元気いっぱいにする」という夢は、日本においても海外においても遠い将来を見据えた事業である。植えてから数十年かけて成木になる緑化事業は、一代で完結させることはできない。それゆえに、次世代につなげていく役割はまさに使命だといえるだろう。

「100年後には、世界中で緑が元気に根付いているように、自分はそのきっかけになれたらいいなと思う。自分がいなくなった後でも木は大きくなり続けて、生物を守るために活躍していけるように。次の世代の人たちはもっと楽しく、動物と植物が共存していけるように。」
そのために、河内氏はさらに新しいビジョンを描き始めている。伐採するたびに出る赤字を助成金などで補填してきた地域の林業に対して、費用対効果が低い樹木ではなく、庭づくりに活かせるような、観賞に人気のある、例えば紅葉する木々の植樹を勧める。「落葉系の紅葉樹は自ら種をどんどん落として増えていく。そうした樹木を育てていけたら山の風景も変わり、より多様性のある緑化に挑戦できそうです。」
世代を超えて生き続ける緑化に向けて、行動あるのみ。その中からこそ、河内氏の役立つ発想は生まれ磨かれていく。堺の森の中の営業所が完成する頃には、どのような事業が展開されているのだろうか。地域の土にしっかりと根ざしながら成長していく、株式会社Kei'sの緑化事業の未来に大いに期待したい。