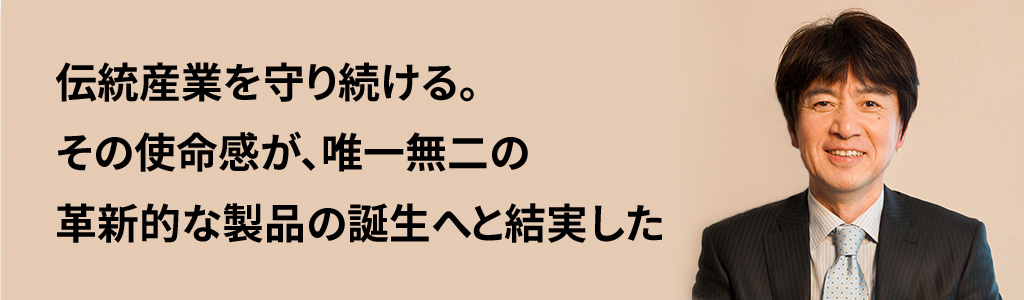Sony Bank GATE
ストーリー
越前和紙や越前漆器、越前焼など伝統工芸品の集積地として知られる福井県において、700年の歴史を持つ越前打刃物。刀づくりの伝統的な技法や手仕事を今に残し、1979年には刃物産地として全国ではじめて経済産業大臣指定の伝統的工芸品に認定されている。この越前打刃物の技法を受け継ぎ、あえて伝統的な手技、機械に頼らない手仕事にこだわりながらも、オリジナル性の高い革新的な製品を生み出しているのが、福井県越前市で70年の歴史を有する株式会社龍泉刃物。国内のみならずヨーロッパを中心に諸外国からも高い評価を受けている同社の製品、伝統的なものづくりを継続しつつ先進的な取り組みにもチャレンジする思いを、代表取締役でありプロデューサー兼刃付師でもある増谷浩司氏にうかがった。
分業制から一貫生産の企業への転換がブランド力のあるオリジナル製品を生み出した
研磨士として高い技術で知られた祖父の代から越前打刃物の製造に携わり、増谷氏の父親である先代が1953年に龍泉刃物製作所を創業。以来、伝統技法を基本にしながらあらたな原材料を用いた製品開発などにも取り組み、高品質な刃物の製造を続けてきた。近年でこそオリジナル製品が2013年から2017年までグッドデザイン賞を5年連続受賞するなど、龍泉刃物の名が世界に知られるようになったが、伝統産業に携わる多くの企業がそうであるように、同社もまた厳しい時期を乗り越えてきた歴史がある。

「日本刀づくりに例えるならば、刀鍛冶がいて刃付士がいて鞘をつくる人がいるように、越前打刃物も分業制が基本です。もともと弊社も分業制の刃物に携わる会社としてスタートしました。しかし、父親の『分業ではなく一貫した生産を目指していこう』という思いのもと、私が会社を受け継いだのが2008年のことでした。以来、鍛冶屋的な製造部門を社内に取り込んで一貫生産を行うようになったのですが、当時はまだ、地元の卸問屋さんと取り引きしながら包丁のOEM生産に取り組んでいました。しかし、低価格の製品が市場にあふれる中、伝統工芸品は買い控えされるようになり、在庫は増えるけれど製品が売れない状況が続きました。すでにその頃、他の刃物産地では伝統的なものづくりから離れ、新しいものに特化した大量生産へと移行する会社もありました。しかし私は、越前市という伝統工芸品の産地を衰退させないためには、あえて伝統的なものづくりを継続する必要があると強く感じていたのです。そこで、大量生産はできないけれども、他のメーカーとは一線を画すようなオリジナル製品を提供しようと、新しいものづくりに挑戦することを決めたのです。」

海外マーケットへのチャレンジが功を奏し、大きなターニングポイントとなった
2009年、オリジナル製品の第一弾として、プロの料理人の意見を参考にしながら研究開発を行い、美しさと切れ味を極限まで追求した包丁『丹巌龍』シリーズを発売。刃の表面に浮かび上がる優美で繊細な波紋は、ふたつとして同じものがない手打ちによるもの。この『龍泉輪』と呼ばれる模様は、龍泉刃物のオリジナルブランドである証でもある。また同じ頃、増谷氏はあらたな販路、販売拠点を海外に求めようと自ら行動に出る。ターゲットに選んだ国はドイツであった。
「私がこの業界に入った当時、刃物・包丁・ナイフと言えばすべてにおいてゾーリンゲンなどドイツの製品が世界最高峰ブランドとして位置付けられていました。そのドイツで弊社の製品を認めていただければ世界に通用するのではないかと。そこで、ドイツのフランクフルトで開催される世界最大の消費材見本市である『アンビエンテ』に出展したのです。」
1年目はなかなか実績が出せなかったものの、2年、3年と挑戦を続けるうちに製品が評価され、海外の取り引き先からオファーを受けるようになる。龍泉刃物にとって第1のターニングポイントとなる出来事だった。また、2013年にフランスで開催された『ボキューズドール世界料理大会』に参加する日本代表用に作成したステーキナイフ『アシンメトリー SK01』が各国の審査員間でも評判になり、龍泉刃物の名が世界に知られるようになったのだ。

「日本代表として参加される料理人のかたに『日本刀をイメージしたテーブルナイフをつくれないか』というお話をいただいたのがきっかけでした。そのかたとは全く面識がなかったのですが、OEMで包丁をつくっている中でたまたま弊社の名前が彫り込んだ包丁をご愛用いただいていたらしく、その名前をたどって弊社に連絡をいただいたのです。そのお話をいただいてから1、2年開発を続けていく中で、これならいけるぞという製品ができたことが海外に向けての大きな発信、龍泉刃物の名前を知っていただく大きなターニングポイントではなかったかなと思っています。」
この出来事によって同社のステーキナイフ『アシンメトリー SK01』は、多くのメディアに取り上げられ、国内外での知名度が一気に高まった。その後、従来の包丁やナイフ製品に加え、カトラリーやステーショナリーの製造販売も開始。現在では国内はもとよりドイツをはじめ、オランダ、スイス、フランス、ベルギー、イタリア、ロシア、イギリス、フィンランド、オーストリアなど12ヶ国・地域にある店舗と直接取り引きするまでに成長した。

伝統産業を守り続ける思いが、革新的な製品づくりを後押しする
現在、株式会社龍泉刃物では一部の製品を除き、海外との直接取り引きに加え、自社のECサイト、直営店にて販売を行っている。また、製造販売に注力するだけではなく、同社が大切に考えているのが、先々代から継承された「砥ぎ」の技術を用いたメンテナンスである。プロ仕様の製品を多く扱う同社にとってメンテナンスサービスは顧客の利用継続、新規顧客の開拓にも力を発揮しているという。
「10年、20年と製品を使っていただく間に、何度も砥いでいくうちに包丁は徐々に細くなっていくわけですが、自分の手の延長のような感覚で、愛着を持っていただける製品をお渡ししたい思いでメンテナンスに取り組んでいます。結果、弊社の製品を長くご愛用いただき、あらたにお求めいただくケースも多いですね。」

基本的に砥ぎ直しは自社製品に限られるが、2019年にオープンした直営店『RYUYSEN FACTORY&STORE』では他メーカーの包丁にも対応しているという。
「インバウンドのお客さまを迎え入れる場所をつくりたい思いと、弊社のクオリティを知ってもらうための作業体験ができる施設としてオープンしたのですが、お客さまの声を直接聞ける場所でもあります。その中で、他のメーカーの包丁を使っているけれども、もう少し長く使いたいというご要望があれば、弊社で修理してお渡しするケースも少なくありません。そうすると、うちの包丁を予備として1本欲しいと購入してくださるお客さまもいらっしゃるんです。これまではプロの料理人が中心でしたが、一般のかたも含めてご愛用いただいているお客さまが少しずつ増えている実感はありますね。」
製品の販売を通じて海外の人たちと交流を持つようになった中、増谷氏は自社の「砥ぎ」の技術を文化交流のひとつとして世界に広めたいと考えているという。
「会社の利益になるようなものではありませんが、今お話をいただいている中で検討しているのがフランスでのメンテナンスです。フランスへの弊社製品の出荷数が増え、日本の包丁を使っていただく環境がようやく整ってきたのですが、やはり砥ぎの技術が違うんですね。現地の人でも粗いメンテナンスはできるのですが、砥石で砥ぐという行為がなかなかできなくて。理想としては、日仏交流団体を通じて弊社の若い職人を現地に短期間派遣し、日本の研磨の文化を伝える活動をやってみたいと思っているんです。それとともに、職人がものづくりだけに励むのではなく、自分がつくった製品の素晴らしさを海外の人たちに直接伝えられるようになって欲しい。そんな職人を育てたいという思いもあるんです。」

日本の伝統技術にこだわり、美しさと機能性を兼ね備えた製品づくりを真摯に続ける株式会社龍泉刃物。代表取締役でありプロデューサーでもある増谷氏の願いは、越前打刃物の技術を後世に伝えることだけではなく、魅力的なプロダクトを生み出すことによって伝統産業を守り続けることではないだろうか。増谷氏の言葉と行動には、そんな使命感ともいえる思いが感じられるのだ。