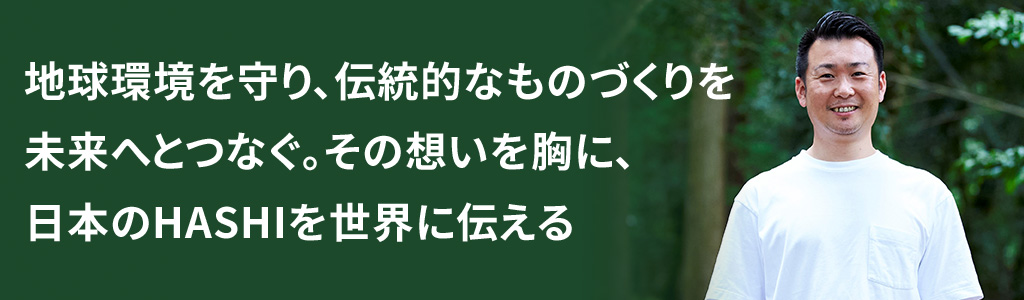Sony Bank GATE
ストーリー
貝殻や卵殻をさまざまな色の漆で何度も塗り重ね、丹念に磨き上げることで幻想的かつ美しい海底の様を描き出す。そんな独創的な技法を用いてつくられる若狭塗箸は、福井県小浜市で400年以上もの歴史を持つ伝統工芸品である。同市に拠点を持ち、オリジナル若狭塗箸や各種木箸などの企画・製造・販売を行っているスタイル・オブ・ジャパン株式会社では、伝統を重視しながらも、現代的な視点や未来志向のコンセプトのもと、「HASHI(箸)」をチョップスティックスに代わる世界共通用語として広めることを企業理念に掲げ、グローバルに展開している。人と自然とが共存共栄するサステナブルな塗箸工芸を目指す熱き思い、独自のビジネスモデルとその展望を代表取締役の大森一生氏にうかがった。
400年の歴史と伝統を持つ若狭塗箸の産地に生まれた誇りを胸に起業を決意した
日本一の塗り箸産地である小浜市で、祖父の代から続く産地問屋で生を受けた大森氏は、高校を卒業するまで、この地で育った。歴史学を専攻するため大阪の関西大学へ進学。その後、経営学を学ぶためにアメリカの大学院へと進み、2003年にニューヨークで起業。現地の食器店やセレクト雑貨店にて若狭塗箸の販売を開始した。店舗への営業活動も含め、たったひとりでの船出だった。
「小さい頃からお箸に囲まれて育っていましたから、将来は箸屋になるんだという心構えが早くから自然と身に付いていた気がします。なので、アメリカでの起業は若狭塗箸が現地で受け入れられるかどうか、その可能性を探るためのマーケティング目的でした。」

現地のJETROの門を叩いて指導を仰いだというが、20代前半の若者が異国の地で起業し、自ら店舗に飛び込み営業を行うには相当なバイタリティが必要なはず。和食ブームという追い風もあったが、本人の努力の甲斐もあり、少しずつ取扱店舗数は増えていったという。
「この頃は販売することやリサーチに時間を使っていたのですが、一方でそろそろ販売したい商品を自分でつくらなければいけないとも考え始めていました。ただ、つくることに関して私は門外漢ですから、帰国して産地で学ばなければならない。自分がつくりたいものをつくり出すためのしくみをつくらなければいけない。そう考え、帰国して起業し、商品をつくることを始めたのです。」
2005年6月、大森氏は故郷の小浜市にてスタイル・オブ・ジャパン株式会社を設立。この社名には2つの思いが込められているという。
「スタイル・オブ・ジャパンとは、日本流や日本様式という意味を持っています。特にお箸においては、日本が誇る美しくモダンなデザインに加えて、機能性や品質などにこだわり、世界的に最適化していきたいという思いがありました。もうひとつの思いは、かつて大航海時代に日本の漆器が世界中に輸出された歴史がありますが、その当時のヨーロッパでは漆器がジャパンという言葉で表現されていた。日本の漆器が世界を席巻した時代と歴史があるんですね。その歴史的な功績に私もあやかりたい、世界にお箸を届けたいという思いを持って命名した社名なのです。」

ドイツの国際見本市「アンビエンテ」での評価が世界進出の足がかりに
塗り箸が地域資源でもある小浜市では、箸の製造において分業制が確立されている。作家性の強い職人がひとりで仕事をする工房から、100人規模の大規模な工場もあれば、製造工程のひとつの作業に特化した職人もいるという。そんな地域の特性を生かし、同社では工場を持たずに製造業としての活動を行うファブレスメーカーとして、商品特性やブランドごとに製造チームを変えて商品づくりを行っている。会社設立からしばらくの間は、国内での販路拡大に力を入れていたため、輸出に取り組むことはできなかったが、2015年に初めて出展した国内展示会で知り合った香港のエージェントを通じて間接輸出を開始。その一方で、エージェントに任せるだけではなく、自ら海外に向けたブランディングを進めなければいけない。伝統だけではなく、あらたな価値を持った箸を生み出す必要性を強く感じるようになったという。
それを機に、ヨーロッパ進出に向けてあらたなコンセプトづくり、商品開発を始めていく中、同社にとってエポックとなったのが、ドイツ・フランクフルトで開催される世界最大規模の国際消費財見本市『アンビエンテ 2019』への出展だった。同社が出品した、福井県産杉を使った箸とスプーンのセット商品『Balance(バランス)』が、審査員投票で1位を獲得。国内外のメディアに取り上げられて一気に知名度がアップしたことで、新規の取引先が増え、展開国もドイツ、フランス、アメリカへと拡大していった。

「実は前年の2018年にも参画しているのですが、その時は力不足で、あっという間に終わった感覚でした。力不足の原因を考える中、われわれに足りないのはデザイン経営の観点だと。なぜ私たちは、これをつくるのか? どうしてこの商品を売りたいのか? なぜこの価格なのか、といったことを含めて改善を図るために『デザインセンターふくい』で学び、よりコンセプチュアルな商品づくりに取り組んだのです。その結果、賞をいただくことができたと思っています。」
出品した商品『Balance』のコンセプトは、人と自然との共存共栄。有効活用できる身近な資源である間伐材を材料に用い、400年の歴史を持つ産地の伝統を次の100年に継承するためのストーリーをつくり上げ、デザイナーにドイツ人を迎えたことで西洋の技術をローカライズしてデザインに落とし込んだ。さらには、SDGsへの取り組みやエコフレンドリーな制作現場の様子を動画などで伝えたという。
「うれしかったのは、次の100年に伝統を渡していくための取り組みも評価されたことでした。人と自然との共存共栄という姿勢も評価されたのだと思っています。」
大森氏が思い描いてきたサステナブルな発想、それを表現したプロダクツが評価され、世界に認められた瞬間だった。

「CO2を減らすお箸」を目指したブランド箸『hashi-coo』を世界へ
現在、日本で流通している割り箸は約250億膳。その90%以上が中国などからの輸入に頼っている。小浜市では年間1億膳の塗り箸を製造出荷しているが、99%は海外から輸入した木材でつくられたものだという。つまり、素材から純国産の箸は1%程度しか存在しないのだ。
無計画な森林伐採、船舶による木材の輸送、製造工程で発生するCO2…。箸づくりがCO2の排出による気候変動に影響を与えているのではないか。そんな気づきから生まれたのが、「つかう人が増えるほど、CO2を減らせるお箸」というメッセージを持つブランド箸『hashi-coo(ハシコ)』である。

原材料はCO2を吸収しなくなった樹齢40年以上の木を間伐したもの。400年の歴史を受け継ぐ箸職人が「研ぎ」や「塗り」を施し、竹の割り箸のように漂白剤も使用しない。製造工程も見直してCO2の排出量を抑制する。パッケージは製造工程でCO2削減に取り組む資材メーカーのものを採用。役目を終えた箸は回収して粉砕し、堆肥として里山の森に返す。これらの取り組みや、間伐によって森林が吸収するCO2量が向上することの結果として同社では、『hashi-coo』によって年間383,600kgのCO2削減を目標に掲げている。
なお、『hashi-coo』はコンセプトや用途の異なる3タイプをラインアップ。
『one time』は、お祝いごとやケータリングなど一度だけ使用したい場面におすすめの、おもてなし用の無垢の割り箸。業務用というコンセプトもある。
『one month』は、1ヶ月ほど繰り返し洗って使える蜜蝋仕上げのお箸。若狭塗の職人が天然由来の蜜蝋を1本1本薄く塗って防水性を高めている。
『one year』は、天然塗料の漆を塗り重ねて耐久性を高めたお箸。ご家庭用や贈りものとしても使える伝統工芸品としての特徴が色濃いお箸となっている。

「この『hashi-coo』に込めたメッセージは、弊社のミッションでもある、地球で一番環境に優しいHASHIブランドとして、環境に優しく持続可能な工程でつくり出されたHASHIを提供することと、CO2の削減です。
お客さまが商品を買っていただいた時点で自動的に、かつ無意識のうちにCO2の削減に貢献できている。使う人が増えれば増えるほど、CO2削減につながるわけです。現時点では日本で使われている塗り箸の99%以上が海外からの輸入木材に由来しますが、われわれの『hashi-coo』に置き換えることで、さらにCO2の削減が加速するはず。そして将来的には、箸をつくる際に排出するCO2量よりも吸収する量を多くするカーボンポジティブを実現する箸ブランドになりたいと考えています。」
近年、世界各地で異常気象による自然災害によって甚大な被害が発生している。その異常気象の一因は温暖化を促進するCO2などの温室効果ガスであることが指摘されているが、脱炭素への取り組みは待ったなしの状況にありながら、なかなか思うように進んでいないのが現実だ。もし、世界の3人に1人が使っているというお箸がCO2削減につながるのならば、きっと私たち一人ひとりが微力ながらも地球環境を守ることに貢献できるはず。スタイル・オブ・ジャパン株式会社の『hashi-coo』は、そんな私たちの思いを具現化してくれるプロダクトのひとつになることを期待している。