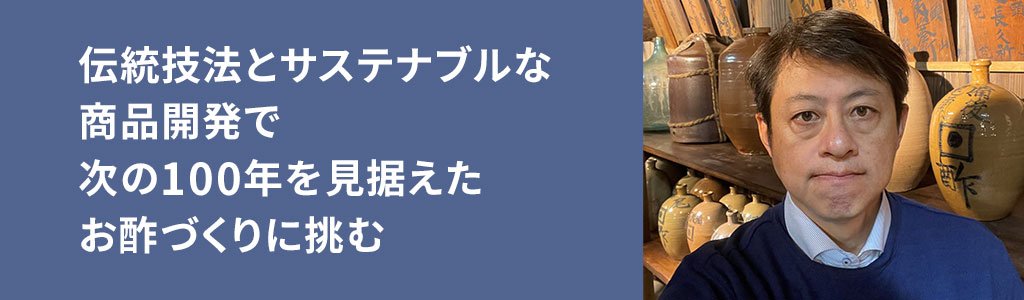Sony Bank GATE
ストーリー
広島県南東部に位置し、瀬戸内海に面した尾道市。古くから海運による物流の集散地として栄えた町であり、近年は数多くの名作映画のロケ地としても知られ、1990年に愛媛県今治市まで続く長距離サイクリングロード「しまなみ海道サイクリングロード」が開通してからは多くの外国人観光客の人気スポットにもなっている。この地において1582年に創業以来、440余年もの歴史を紡いできた尾道造酢株式会社。伝統技法を受け継ぎながら、時代のニーズにあった新商品の開発にも取り組む同社の取締役である田中丸善要氏に事業内容やこだわりのお酢づくり、描いている未来についてうかがった。
創業時から受け継ぐ「酢酸菌」を守り、伝統技法によるお酢づくりにこだわる
尾道市では江戸時代からお酢づくりが行われるようになり、この地で生まれた上質なお酢は北前船によって全国へ届けられたという。その当時から開業していた尾道造酢株式会社は、日本に現存する最古のお酢醸造所のひとつとも言われている。同社の歴史を語るうえで欠かすことのできないのが、お酢の原料を発酵させるために用いる「酢酸菌」。同社では、生き物を育むのと同じように創業当時から受け継がれた酢酸菌を繁殖させながら使用しているという。
「1年365日、毎日面倒を見ています。菌が伸びているのが元気な状態なのですが、そうではない菌を見つけたら網で掬って捨てる必要があるのです。そして、掬って取り除いた場所に元気な菌を植えてあげると、翌日にはアルコールを餌にどんどん酢酸菌が増殖していくんですよ。本当に生き物なので、放っておくと自分の重さで沈んでしまうんですね。沈んでしまった菌は匂いの元になるので当然お酢の匂いも変わってしまいますし、弊社の味をつくり出すことができなくなってしまうのです。」

この手間のかかる作業を田中丸氏と工場長の2人が担うことで、創業以来の酢酸菌を守り続けている。さらに同社の特徴とも言えるのが、主流である機械製法に頼らず、自然の発酵方法に分類される独自の「水平式連続発酵方法」を採用している点にある。
「1955年に特許を取った製法になります。当時、お酢を大量に生産する必要が生じたのですが、以前から採用していた方法では発酵に2ヶ月ぐらいかかってしまうため、とても生産が追いつかない。そこで、ゆっくりアルコールを流しながら発酵させていく表面発酵を用いれば、毎日お酢をつくることができる。それが、水平式連続発酵方法です。効率化が進んだ現代のお酢の製造法と比較すればもちろん手間はかかるのですが、独特のまろやかな風味を出すために、今も弊社はこの方法でのお酢づくりにこだわっています。」

生産性と効率性を追求するならば機械製法を採用するべきだろうが、それでは江戸時代から続く味が損なわれてしまう。たとえ手間がかかろうが、自分たちにしかできないお酢をつくるために伝統技法を守り続ける。それが同社のこだわりであり、匠の技を持つ職人たちの矜持が、それを支えているのだ。
顧客のニーズに応えるお酢の開発により数多くの商品ラインアップが誕生
同社が「水平式連続発酵方法」を開発するきっかけとなったのが、1955年に開始した大手マヨネーズメーカーのマヨネーズの原料酢の提供だった。
「すでにその頃、弊社では西洋酢と呼ばれるシードルビネガーというリンゴ酢をつくっていましたので、この酢を原料として提供したのですが、納得のいく味にはならなかったそうなんです。そこで『開発費はいくらかけてもいいから。』と言われ、海外へ視察に行ったり、欧米のマヨネーズの原料を調べたりしながら開発したのが、大麦麦芽を使ったモルトビネガーというお酢でした。これはイギリス発祥のお酢なのですが、このモルトビネガーとリンゴ酢を合わせることで理想のマヨネーズをつくることができたそうなのです。そこで、この2種類のお酢が採用され、納品することになったのです。」
ところが、徐々にマヨネーズの生産量が増加していったことで、同社だけではお酢の生産が間に合わない状況に陥ったという。その結果、1962年に同社を含む4社によって現在のキユーピー醸造株式会社の前身となる会社が設立されてマヨネーズの原料となるお酢の生産を担うようになり、取引は終了することとなる。その後、同社では、業務用のお酢をその店が求める味に仕上げたオーダーメード商品をつくるなど、独自のスタイルで商品ラインアップを増やしていくようになる。そんな顧客のニーズに応える形で開発されたのが、同社のベストセラー商品である調味酢「そのまんま酢のもの」である。

「この商品は1990年から製造しています。女性も働きに出ることが当たり前の時代になり、料理に時間をかけられなくなったことで、お酢に砂糖を加えたりしながら自分で調味酢をつくることが大変な作業になっていきました。実際、当時は調味酢に関する問い合わせが多数あったことから開発を始めたと聞いています。万人に合う調味酢はないと思うのですが、少し甘めにつくっておけば、酸っぱさが物足りないかたはお酢を足すことで味を整えることができる。そんなコンセプトで開発した商品です。その後、おかげさまで『そのまんま酢のもの』は口コミで全国に広まり、現在まで続く弊社の看板商品となっています。」
SDGsの観点から誕生した果皮酢飲料「KAHISU」
尾道市では地域性豊かな農産物が数多く栽培されており、無花果、レモン、ネーブルオレンジ、モモ、ブドウ、デコポン、串柿などは国内でも有数の生産量を誇る。このような尾道市ならびに広島県産の果実などを原料に取り入れているのも同社の特徴であり、こだわりである。その背景には、尾道産の食材を全国に広めたいという想いに加えて、食品ロスの削減に貢献したい想いもあるという。このような発想を起点に誕生したのが「飲む酢」シリーズの「無花果酢いーと」「柿酢いーと」「葡萄酢いーと」である。

「これらの商品は地元の農家さんの声から生まれました。無花果は尾道の特産品で、実が開いた時がいちばん美味しいんですよ。ところが実が開いた無花果は青果として扱ってもらえず廃棄処分となってしまう。その状態の無花果を弊社が仕入れて商品化したものが飲む酢シリーズです。いちばん美味しい状態の無花果を安価で仕入れられるのは弊社にとってメリットでもありますし、農家さんにとっても無駄をなくすことにつながるので喜んでいただけています。単なる「無花果酢」や「柿酢」では、なかなか手に取っていただけないでしょうし、何に使えばいいのかわからないと思うんですね。そこで、普通のお酢として売り出すのではなく、飲むお酢として開発しました。最近では、健康志向の高まりによる飲むお酢ブームが起きたことで弊社の「飲む酢」シリーズの認知度も高まり、販売量が増えつつある状況です。」
また、同社では地元である尾道市への地域貢献により力を入れていくため、2021年にSDGs宣言を行った。その背景には、搾りポン酢の原料などに使用している橙の皮の廃棄問題が関係していたという。

「毎年冬になると30トン近い量の橙を搾るのですが、搾った後の皮はすべて廃棄していました。搾汁率が15%程度しかないため、残り85%を廃棄していたことになります。廃棄には費用がかかりますし、ゴミとして処理されることでCO2の排出量を増やすことにもつながります。何か有効活用できないかと考えていたときに、広島県食品工業技術センターの研究員のかたから、柑橘の皮を酵素で溶かしその果皮汁を発酵させお酢をつくる方法があることを教えていただいたんです。その後、工場で試行錯誤を重ねてお酢をつくることに成功し、新しい商品が出来上がりました。弊社は小さな企業ではありますが、フードロス削減や地球環境の改善に向けて取り組んでいることを知っていただきたくて、SDGs宣言を行いました。」
このSDGs宣言後、ひろしま感性イノベーション推進協議会事業として編成されたプロジェクトチームの一員として開発したのが、廃棄される搾汁後の皮を果皮酢として再生させた果皮酢飲料「KAHISU」である。この商品は2023年に開催されたG7広島サミットにおいて提供されるなど、従来のビネガードリンクとは一線を画す深い味わいが高評価を得ているという。まさに温故知新。伝統を大切にしながら、新しいことにも果敢にチャレンジしていく同社の企業姿勢が生み出したオリジナル性の高い商品である。

100年後も存続する会社であるために新たな商品開発にチャレンジし続ける
同社では2年前から自社サイトでの通信販売を開始した。これもまた新たな販路の開拓を目指す、同社のチャレンジのひとつである。
「以前は個人のお客さまからの電話注文による売上が年間で2,000万円くらいありました。ただ、既存のお客さまの高齢化もあり、徐々に電話注文による売上が減少する状況となっていました。時代の変化に合わせて自分たちも変わらなければ、という思いがあり、オンラインストアを始めたのです。売上的にはこれからという感じですが、やはりオンラインストアを利用されるお客さまは若いかたが中心ですし、「KAHISU」目的に利用されるかたも多いんです。新規のお客さまの開拓に向けた取り組みという意味では、重要なコンテンツであると考えています。」
440年を超える歴史を未来につなげるため、先人から受け継いだ伝統技法に加え、新たなエッセンスを加えてオリジナル性の高い商品をつくり続ける同社。その歴史を紡いでいくキーパーソンである田中丸氏は、どんな未来を描いているのだろうか。

「基本的には、これまでと変わることなく丁寧にお酢をつくり続けていきたい、と考えています。その中で、大きな会社にはできないようなチャレンジをやっていきたいと思っているんです。例えば、直近では広島県の特産品であるレモンや柚子の皮を原料にした果皮酢の開発を進めています。まずは、果皮酢をメジャーな存在にすることで、原料である尾道の果実にも注目していただけるようになるとうれしいですね。」
尾道には昔から酢漬けの食文化があり、料理によくお酢が使われる風土があるという。尾道造酢がその文化の一翼を担ってきたことは間違いない。地元の人に愛されるお酢を丁寧に、ひたむきにつくり続けてきたことによって、創業から440余年という途轍もない歴史と伝統を紡いできたのだと思う。そんな長い歴史を拠り所にするのではなく、未来に向けたサステナブルで画期的な商品の開発に取り組んでいる同社、そしてお酢の可能性を広げる新商品に期待したい。