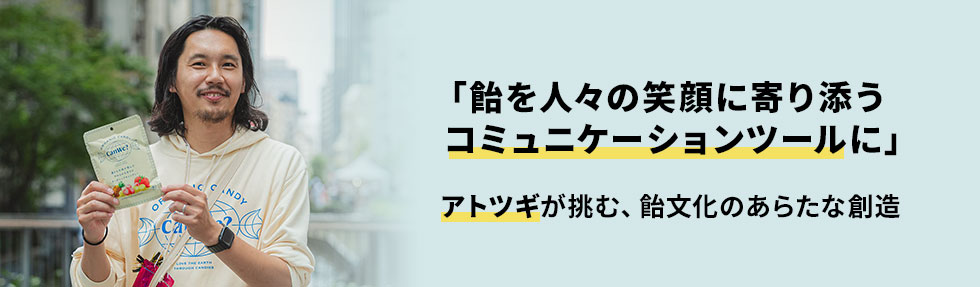Sony Bank GATE
ストーリー
日本有数の菓子メーカー・菓子問屋街として知られる名古屋市西区。この地で60年以上にわたり菓子問屋業を営む株式会社ナカムラ。近年は、問屋業に加え、江戸時代から続く伝統菓子「組み飴」を企業のノベルティ用にオリジナルデザインでオーダーできるサービス「myame(まいあめ)」の運営や、日本初のオーガニックキャンディーなどユニークな商品開発でも注目を集めている。飴作りの伝統技術を後世に残すための取組、商品を通じて飴のあらたな価値創造に挑んでいる同社のアトツギである専務取締役の中村慎吾氏に、事業にかける想い、画期的な新商品とその展望についてお話を伺った。
飴を「メディア」と定義し事業をリブランディング
名古屋市西区で生まれ育ち、現在はアトツギとして株式会社ナカムラの事業を牽引する中村氏だが、そもそも家業を継ぐ意思はなかったという。そのため大学卒業後、ジーンズメーカー勤務を経て、マーケティング会社に入社。しかし、この2社での勤務経験が、働くということへの意識を変えた。仕事を通じて社会貢献したい想い、経営者的な立場で事業に携わりたいという気持ちが高まり、家業である株式会社ナカムラに入社。2017年のことだった。

「社員として働くことは、もちろん魅力的ではあるのですが、それ以上に社会貢献したい気持ちが強かったんです。しかし最初に勤めた会社では、その想いを実現できないことがわかり、転職した会社でマーケティングに携わる中で、自分で事業を担いたい気持ちが生まれてきました。それは、子どもの頃から、一生懸命仕事に励んでいる両親の姿を近くで見ていたことも影響していたのかもしれません。当時の上司からの後押しもあり、今ならこれまでの経験を生かせるのではないかと思い、家業を継ぐ決意をしました。」
同社の事業の柱は、創業時からの駄菓子卸売業務である。だが、2007年にスタートした切っても切っても同じ絵柄が出てくる「組み飴」のオーダーメイドサービス「myame(まいあめ)」事業が多くのメディアに取り上げられたこともあり、同社の認知度は一気に高まっていった。「まいあめ工房」として始まったこの事業を社長である父親から受け継ぎ、国内外の有名企業と取引するまでに拡大した立役者が中村氏である。

「父が仲良くしていた飴職人さんがいるのですが、高齢化など職人さんの課題もさまざまある中で『この技術を失うのはもったいない』という話になり、職人さんとその技術が輝けるサービスという趣旨でスタートしたのが『まいあめ工房』です。よく大阪の女性が『飴ちゃんいる?』と言って渡すことが知られていますが、『飴ちゃん』と擬人化される食べ物ってなかなかないですよね。お菓子だけれど親しみをもって『飴ちゃん』と呼び、誰かに渡そうとする。そんなことから父は『飴は立派なコミュニケーションツール』だとよく言っていました。入社後、私がリブランディングするにあたり、父が言っていたコミュニケーションツールとしての機能を前面に打ち出し、言語化したうえで食べられるチラシのように使っていただこうと考えました。飴は他のチラシと違い、視覚・触覚だけではなく、味覚・嗅覚にも訴えることで記憶に残り、なおかつ人を笑顔にするメディアであると。そこで弊社では、飴を単なるお菓子ではなくメディアと定義し『myame(まいあめ)』としてブランド展開しています。」
キャンディーのオーダーメイドサービスに国内外の有名企業が注目
お菓子のプロデュースカンパニーである「myame(まいあめ)」のオリジナル商品は、代表的な「組み飴」をはじめ、小さいサイズの組み飴「プチ飴」、「ペロペロキャンディー」、「3Dキャンディー」、「キャンディケーン」の5タイプ。これらは職人の手作業で作られる、オリジナル商品となっている。なお、「myame(まいあめ)」事業は、ネットでの集客で成り立っており、多くがリピーターの顧客だという。用途はそれこそ千差万別だが、現在までに約10,000を超える企業・団体からの注文を受け、ロゴやキャラクター、メッセージを組込んだ飴を販売している。顧客は国内企業にとどまらず、SNSを活用したプロモーションに着目した世界的なテック企業もいるという。

「世界的なテック企業各社も弊社のお客さまです。また、国内企業も大手企業からスタートアップまで本当にさまざまです。その中で、とても印象に残っているお客さまは、大手とんかつ飲食店さまとのお取引です。周年記念として全店での配布用に弊社の組み飴をご注文いただきました。かつてない、40万粒という大量のご注文だったため生産が大変だったのですが、この案件を通じて生産を依頼しているメーカーの若手職人の技術が一気に向上した事例でもありました。また、最近印象的だったのは、建設業界向けに建築図面・現場管理アプリを提供されている企業さまから、現場で働くかたがた向けに塩飴をご注文いただいた案件でした。飴を使って自社アプリの宣伝もしつつ、作業員のかたがたの健康にも配慮するという企画が素晴らしいなと思いました。同様に、販促やPRではなくCSRの観点で利用したいというお客さまが非常に多くなっています。」

現在、多くの需要に対して生産体制を強化するべく、製造委託先のメーカーと協議しているという。それは、同社が打ち出した「飴はコミュニケーションツールでありメディアである」というマーケティング戦略が、多くの企業に認知され共感されていることの証だといえる。
環境負荷の低減をコンセプトに 日本初のオーガニックキャンディーを開発
昨年、同社ではあらたな挑戦として、「myame(まいあめ)」とは異なるコンセプトのもと、一般消費者向けの商品として、日本初のオーガニックキャンディー「CanWe?」を発売。オーガニックキャンディーは健康面への好影響が期待されるだけではなく、非オーガニック飴購入に比べ、CO2の44%削減貢献が可能なのだという。まさに、食べることで環境負荷の低減に貢献できるキャンディーである。

「元々2019年頃から『環境に良いキャンディーはないですか?』という問い合わせが非常に増えてきた背景があり、オーガニック原料を扱う商社からオーガニック市場などについて話を聞くようになっていたのです。もともと興味を持っていた分野ではあったのですが、2020年に子どもが生まれたことで環境問題について考える機会が増え、キャンディーの本質的な機能に「環境負荷の低減」を取り入れようと考えたのが理由のひとつ。もうひとつの理由としては飴商品が置かれている現状がありました。コンビニへ行くとわかりますが、のど飴であるとか、ハチミツやビタミンCを配合した健康機能的なキャンディーが多く置かれています。このような商品は大手メーカーが圧倒的に有利であり、中小企業のキャンディーメーカーでは太刀打ちできません。大手が参入しづらい市場で勝負しなければ、伝統的な飴作りの技術を用いた自分たちのキャンディー文化を守ることができない。そんな想いからのスタートでした。」

そこから2年以上かけてオーガニック原料を探し、リトアニア産の砂糖を使用することを決定。ロシアによるウクライナへの軍事侵攻等の影響から原料の輸入がストップする事態に見舞われるなどの苦労の末、商品化に成功。現在、自社オンラインストアとオーガニック商品を扱うスーパーマーケットにて購入できるほか、すでに2社のOEM生産が決まっているという。
さらに同社では、「環境負荷の低減」をコンセプトに、法人向け商品として「カーボンニュートラルキャンディー」を開発。この商品は自社努力によって、従来のキャンディーと比較して製造過程で排出されるCO2を44%削減。残る56%のCO2は「J-クレジット制度(温室効果ガスの排出削減量や吸収量をクレジットとして国が認定する制度。クレジットの売却益を設備投資などの企業活動に利用可能)」の購入に充てられる。そのため、CO2の排出量が実質ゼロのキャンディーになるという。

「この商品も『CanWe?』と同じようにイチゴとパインのフレーバーを用意していますが、今後は塩飴やのど飴などもラインアップすることで、従業員の健康を守りつつ、企業さまのSDGsの取組や姿勢を発信するツールにできればと考えています。すでに数社の企業さまと商談を進めているところなのですが、カーボンニュートラルと健康に寄与するコンセプトが、会社のイメージアップにもつながると、かなり好評価をいただいています。また、現在ではプロスポーツチームさまとノベルティという形で入場者に配布したいというお話も進んでいますし、コラボレーションを希望される企業さまも出てきている状況です。」

脱炭素と言われても、目に見えない気体であるCO2を削減している実感を持つことは難しい。しかし、キャンディーを食べることで脱炭素に協力できるのであれば、難しいことを考えずに誰もが取組めるのではないだろうか。
「そうなんです。単なるキャンディーかもしれませんが、環境について考えるきっかけになるとうれしいですね。この小さな1粒から環境改善につながる、あらたな消費行動を実現できればと考えています。」
SDGsとビジネスの両立は難しいと言われることもあるが、同社ではキャンディーを通じてそれを実現しようとしている。また、同社のキャンディーが企業のSDGs活動を後押しすることにもなるだろう。事業を通じた社会貢献を目指していた中村氏の想いが、少しずつ形になろうとしているのである。
地元・名古屋の駄菓子文化を守り、職人の技術を後世に残すために
2023年12月、同社は近隣にある廃業した銭湯をリノベーションしてオフィスを移転した。旧事務所は自宅の一部をオフィスに改良した狭いスペースだったため、事業の拡大に伴う社員数の増加によって規模的な限界を迎えていた。それも移転の理由のひとつだが、中村氏には地域貢献の想いもあったという。
「この地域は銭湯がたくさんあったのですが、どんどん廃業していくことに寂しさを覚えていましたし、今回、オフィスにした銭湯は私が昔からよく利用していた思い出の場所でもありました。建物を壊すのではなく、何かに生かしたほうが地域の文化やその名残をとどめることになると思いましたし、裸の社交場といわれる銭湯と、飴をコミュニケーションツールとする弊社がリンクする親和性も感じました。また、テレビ番組の取材なども受けるようになっていましたので、銭湯をオフィスにすることで話題になるかもしれない。会社の広報活動にもつながると思い、移転を決めました。」

話題性になるという中村氏の狙いは的中。さらにマスメディアの取材は増え、同社の取組が広く発信されることとなった。また、この広報効果が事業活動や採用活動にも寄与しているという。
「小さい企業ではありますが、注目していただけるのはありがたいですし、大きな意味があると思っています。取材だけではなく、お客さまに足を運んでいただけることが非常に増えましたし、エントランスに設置した足湯は、来社された企業のかたがたも実際に入浴され、たいへん好評です。また、これから会社が成長するにあたっては人材が必要になりますので、採用活動も重要ですが、このオフィスの効果もあって採用面でも有効性がありました。」

環境や地域への貢献にも乗り出し、さまざまなチャレンジを続ける同社。その事業を先導する中村氏は、会社の未来像をどう描いているのだろうか。
「10年後もその先も変わらずに飴の会社でありたいと思っています。子どもたちや、飴を食べている人たちの笑顔に寄り添う飴屋でありたいですね。そのためには新規事業を確かなものにしなければいけないですし、それが名古屋の駄菓子文化を守ることにつながるとも思っています。そういう意味では、職人の手仕事と高品質なキャンディーを残す存在でありつつ、人々にとっては笑顔やコミュニケーションを促す商品を提供できる存在になれたらと思っています。」
アトツギとして日本の飴文化の発展に挑む中村氏。時代の変化に柔軟に対応しながらも本質を見失わない姿勢は、多くの老舗企業にとっても希望の光となるに違いない。